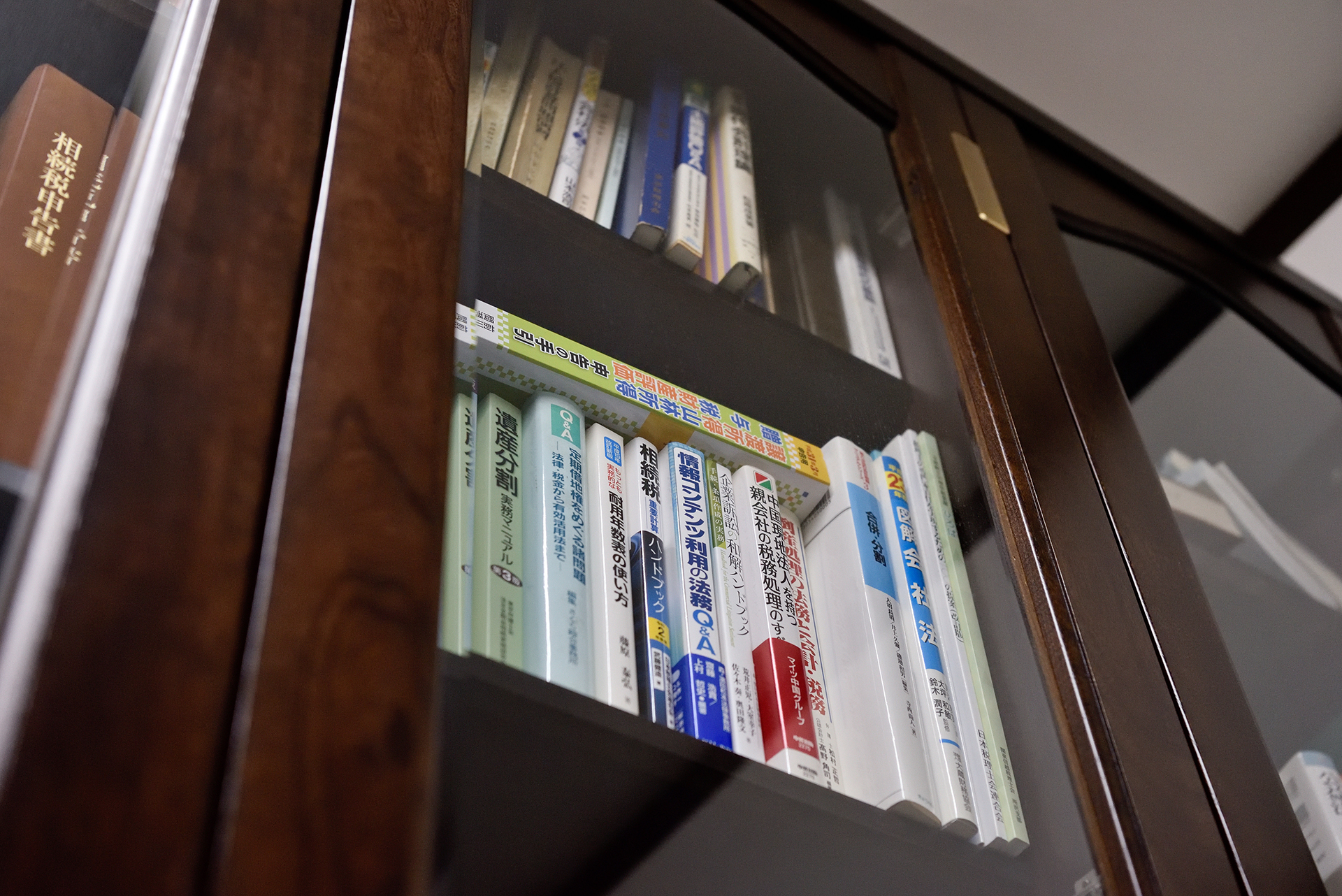税理士に対するご質問
税理士に顧問を頼むメリットはありますか?
税務署の対応は全て税理士が行う。各種試算表等の作成も税理士が銀行等に信頼される書類を作れる。多種多様な相談事に乗ってくれ、アドバイスを受けられる。他業種の状況などを聞ける。節税や資金繰りの相談ができる。経営のアドバイスを受けられる。事業承継などを相談できる。
顧問税理士を選ぶポイントを教えてください。
その税理士が何をできるかが重要だと思います。法人税申告・消費税申告・所得税申告・贈与税申告・相続税申告等々、税金は様々な種類があります。それらは個別の法律で出来ていますが、対象となる人(法人と自然人の違いはありますが)は決まっています。そのため常に横断的に税金を考えている税理士がよいと思います。また、税理士業務は付随業務を合わせると多岐にわたっています。そのため、様々経験や知識を持っている税理士を顧問としておくと多種多様なアドバイスを受けられるメリットがあります。さらに、他士業との繋がりを持っていれば相談事もワンストップ済みます。
公認会計士と税理士の違いは何ですか?
公認会計士と税理士の違いは、公認会計士が上場企業の監査を行い監査報告を利害関係者に報告する。税理士は税金の計算を行い税務署に申告をする。それぞれが法律で認められた独占業務です。ただし、公認会計士は、税法に関する所定の研修を修了することで税理士として登録することが出来ます。
相続に関するご質問
相続が発生した場合、どのタイミングで相談すればいいですか?
通常は亡くなられてから四十九日は個人を偲ぶ期間と考えます。そのため、忌中を過ぎた頃から相談されるのが良いかと思います。ただし、亡くなられてからすぐに相談に来られる方もいます。
相続税の申告期限はいつまでですか?
被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなられた方の住所地の税務署に申告することになっています。
どれだけの財産があれば、相続税がかかるのでしょうか?
相続財産等の合計額から負債の合計額を除いた額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合に相続税の申告が必要となります。ただし、超えない場合でも遺産分割の内容によっては申告が必要になる場合もあります。
事業承継に関するご質問
事業承継の手法にはどんなものがありますか?
事業承継には様々な手法がございます。まずは最終目的を、血縁関係者が承継・血縁関係者以外が承継・M&Aによる承継・解散清算などが承継の最終目的になります。それらを社長のご希望に寄り添った、また会社全体の希望に寄り添った形でどれかの最終目的に向かって進んでいきますが、多種多様な事情を抱えた会社が多いので、その会社に寄り添った方法を模索していきながら最終目的を目指すことになります。そのため、軌道修正は頻繁に起こります。
事業承継を円滑に行うには、いつから検討すれば良いですか。
事業承継は早ければ早いほどよいです。同族会社は上場会社とは違い、社長や株主は変わることがありません。そのため、常に意識して後継者を探すことを考える方がよいと思われます。
赤字、もしくは債務超過の会社でも対応可能でしょうか。
対応可能です。事業承継をする際には会社の分析も行います。その上で、赤字や債務超過の会社でも再生できるようにお手伝いをしながら後継者になる方が継ぎたくなるような会社にすべく経営のアドバイスをしていくことも大事なことだと考えています。